▼ 今回の山行の参考図書。
 幽 2008年 01月号 [雑誌]
メディアファクトリー
メディアファクトリー
幽 2008年 01月号 [雑誌]
メディアファクトリー
メディアファクトリー
▼ 『幽』に連載されていた「怪談巡礼団」の選りすぐり十篇。もちろん上記の「京都の怪」も載ってまっせ。
 ぼくらは怪談巡礼団 (幽ブックス)
加門七海,東雅夫
KADOKAWA/メディアファクトリー
ぼくらは怪談巡礼団 (幽ブックス)
加門七海,東雅夫
KADOKAWA/メディアファクトリー
○
7月6日(日) のち
のち のち
のち
7月の京都といえば祇園祭でおます。エセ京都市民たる者、まずは「八坂さん」へ参社しなければおへん。
その祇園祭の目的がそもそも、疫病の元となる怨霊を退散させるためのものですんで、今回のオイラの道中は「怪談ツアー」めいているのであった。
▼ 8:00 京阪・祇園四条駅に到着。
▼ 8:10 四条通を東進して八坂神社に到着。祭神スサノオと習合されてしまった牛頭天王は、件(くだん)と関係しているのであろうか?

▼ 本殿で道中安全祈願を終えたのちし、末社の美御前社に寄ってみる。身も心も美しくなるという美容水を顔につけて、円山公園へいざ出発。

▼ 円山公園内にある祇園祭山鉾館。普段から閉まっている山鉾収蔵庫です。
▼ シダレ桜ちゃんは、暑さでややしなびれている感じです。
▼ 池にいたカメとアメンボ。
▼ 坂本龍馬と中岡慎太郎像。
▼ 慎太郎氏、横目で覗き見してないか?

▼ 円山公園の奥地に初めて来た。緑にあふれているねえ。
▼ 吉水弁財天の右の道から、いざ山へ。

▼ 半ば乗り捨てられたような練馬ナンバーの日産・マーチBOX。怪しいなあ。
▼ 8:53 「将軍塚道」の石柱が建つここからが本格的山道。
▼ 将軍塚までは、加門七海センセや東雅夫編集長ら「怪談巡礼団」がたどった道でもある。
舗装もされていない山道は、観光地のイメージからはほど遠い。ときどき雑木林の端に、ケルンのように石の積まれた石仏の姿が見えた。(加門七海著「京都結界巡り」より引用)
京都初心者の編集Rが「ここも京都なんですね」と、しみじみ言った。いやいや、この道は、よほどの物好きじゃないと来ないから……。(加門七海著「京都結界巡り」より引用)
▼ 将軍塚がある青蓮院門跡飛地は、護摩壇等の新築工事中で立ち入り禁止でした。
▼ 9:16 東山山頂公園に到着。

▼ 展望台から京都の街並みを見て、しばし休息。写っていないが、五山送り火の「左大文字」と「船形」が見えることを確認。「鳥居形」も見えるんかなあ?

▼ 9:40 防火貯水槽横、京都一周トレイルの「東山20」道標に到着。ここからはしばし「怪談ツアー」を離れ、オイラの興味本位の、まだ歩いたことがない道を歩くことにする。南東方向の道へ進行。
▼ 9:50 東山ドライブウェイと出合う。右に見える標識のところから再度山へ突入。

▼ 最初は急坂。シンドイ。
▼ 10:04 平坦な道になり、進むと、「東山18-2」に出合った。左:清水山、右:東山山頂公園。
▼ おっ! 「子安塔」を指す道標があるぞ。「怪談ツアー」再開。行ってみよう。
▼ 10:14 快調に坂道を下り、清水寺と清閑寺を結ぶ道と出合う。
▼ 以前来たときは、まだ子安塔は改修工事中だったのだが、もう完成しているのか?
▼ ちょっと小ぶりな三重塔。見事に工事が完了しておりました。まばらに観光客がいるし、周囲の怪しさはゼロ。
▼ 清水寺の本堂方向へ進む。
▼ 観光スポットに、汗まみれの汚いオッサン独り。我が道を行くのだ。
▼ 清水の舞台と京都タワーは絵になるねえ。
▼ 10:36 地主神社の右の道から山へ再突入。
▼ これは心霊写真か!? いえいえ、南無阿弥陀仏と刻まれた石柱を写そうとした瞬間、耳元で「ブゥーン」という虫の羽音がしたので、思いっきり手ブレしたのでありました。
▼ 清水寺境内のすぐそばだというのに、誰もいない。
▼ と思っていたら、草木の間を見え隠れしながら、前方を軽装の一組のカップルが歩いている。
▼ 10:47 「東山19」と出合う。ここは分岐なんで、どっちへ行けばいいか迷っている先行カップルに追いついた。
「写真、撮リマスカ?」と女子に声をかけられた。
二人とも外人さんやんか、ヤバい。
彼女は片言の日本語が話せるらしい。「撮りましょうか」と言ったらしいのだ。それじゃと彼にコンデジを手渡すと、彼女が彼に通訳し、撮っていただきました。
道標はあるが漢字表記なので、彼女は読めないのだ。ただし「寺」は読めるらしい。写真のお礼に、「キヨミズ・テンプル」「ヒガシヤマ・マウンテン・パーク」「マウント・キヨミズ」とオイラが流暢なイングリッシュを披露してレクチャーしてさしあげたのは言うまでもなかろう。
「マウンテン・パークニ何アリマスカ?」と訊かれ、「ネコ!」と答えたのは失敗やったかも……。
▼ 10:51 「グッド・ラック!」と言って別れたオイラは、再び「東山20」にやって来た。
▼ さっき通った時は気づかなかったのだが、防火貯水槽の上にカエルの大きな卵がありました。

▼ 次は興味本位に未踏の道を歩く第二弾。北西に延びる道を行ってみよう。
▼ やや荒れの道である。
▼ 谷に沿って細い道を進む。霊感ゼロながら、なんか怪しい道である。

▼ どうしたわけか、あまり進みたくないのだ。……でも、行っちゃいます。
▼ 朽ちそうな橋は慎重に渡ろう。
▼ 時には急な坂道を下り、時には道なき道を進む。
途中、分岐があって登りか下りかを選択しなければならないのだが、オイラは迷わず下りで下山コースを選びました。何とか早く、この道から脱出したかったのだ。
▼ 11:07 墓場に出た! 助かった〜!
▼ 高台寺墓地のようである。水道で顔を洗い涼をとり、しばし休息。
▼ 墓場から見る京都の街もオツなもんですな。
▼ 高台寺墓地と東大谷墓地はつながっているようです。
▼ 下山してホッコリしてしまっているオイラは、帽子を落としていることに気づいていなかった。日傘の親切なご婦人に教えていただきました。おおきに。
▼ 11:44 日本史上最大級の怨霊になったとされる崇徳天皇御廟に到着。

▼ 近くの安井金比羅宮で悪縁の某(笑)との縁切り祈願。

▼ JRAの場外馬券売り場に入って涼をとる。
▼ 弥栄会館。ロビー見学しとけばよかった。
▼ 12:11 京阪・祇園四条駅に無事帰還。でも、何か目に見えないものが、くっついて来てるかもしれまへんなあ。

○
▼ 千二百年の都には千二百年分の怪談があるハズなのだ。怪談好きは、「京都」を深く知れば知るほど好きになってしまうのである。









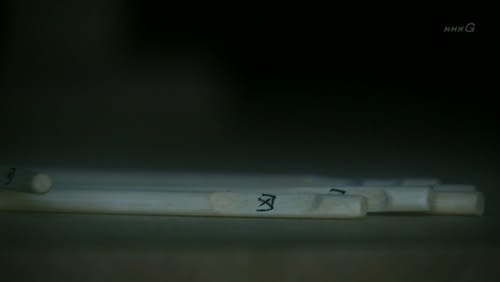



































































































































































































 汗ダラダラ、意識モウロウ、身体ヘロヘロになりながら火床に到着。
汗ダラダラ、意識モウロウ、身体ヘロヘロになりながら火床に到着。

























